|
2016,08,20, Saturday
引続き、”Plant Resins: Chemistry, Evolution, Ecology, and Ethnobotany”を読み続けています。必要な箇所だけ拾い読みするつもりでしたが、植物由来の抽出物全般に関してたいへん詳しく書かれており、もはや全体を読まずにはいられないところです。マスチック樹脂に関しては、メギルプ制作実演と一緒にマスチックについて語るという動画を鳥越一穂氏と収録したので、そのうち公開されるかと思います。鳥越氏自身はマスチックを使用しておらず、コーパルを含む画用液を調合して使っているとか。
しかし、私は今はダンマルについて読んでいます。マスチック樹脂の定義や採取植物についての問題というのも、いろいろ整理が大変ですが、それよりも遥かに混乱しているのが、ダンマルです。ダンマルは絵画用の天然樹脂としてはたぶん最も一般的なものですが、どのような植物から採れるのか、案外はっきりとわからないものです。少なくともマスチックは最良の物はキオス島南島のPistacia lentiscusであるということは、はっきり述べてもいいかと思いますが、ダンマルの方が複雑怪奇です。ダンマルが、というよりは、コーパルも含めて東南アジアの樹脂の名称が全般的に複雑なのですが。 というわけで、”Plant Resin”を読みつつ、私なりに現状の認識で整理していきますと・・・、ダンマルの採取源となる植物ですが、東南アジアのフタバガキ科に属する植物が主たる採取源で、ネット上を検索した限りでもそのように書かれてあることが多いようです。しかし、その他植物の樹脂もダンマルと呼ばれることがあり、用語としてのダンマルは非常に曖昧で混乱を招く原因となっています。”Plant Resins”によると、そもそもはマレー人が樹脂で作った燈火をダンマルと呼び、それが樹脂全般を指す言葉と転訛していったということです。やがてヨーロッパと大規模な取引がされる中で熱帯アジアからの樹脂をdammarと呼ぶようになった云々とあります。  フタバガキ科の他、カンラン科(burseraceae)も挙げられています。カンラン科ではプロティウム属(Protium)、フタバガキ科では、サラノキ属(Shorea)が特に採取源として言及されている。サラノキ属には仏教寺院に植えられることで有名なサラソウジュ(沙羅双樹、学名Shorea robusta)が含まれます。ちなみに、私の自宅にも2本の沙羅が植えられいますが、実は日本の沙羅は、ツバキ科のナツツバキで、耐寒性の弱い沙羅双樹の代用として植えられた為に沙羅とも呼ばれるようになっただけの模様です。ちなみに赤い染料で知られるスオウ、これも日本でスオウという木がたくさん植えられていますが、実はハナズオウというもので花の色が赤いというだけで別の樹木です。アラビアゴムが採取されるアカシアも、日本の北の方にまで植えられていたりしますが、実はニセアカシアという別の木だったりするのと似たような例といえるでしょう。 マレー諸島の東、乾燥した土地の生えるAgathisが、はじめdammaraという属に分類されたそうです。植物の科、属、種などは随時更新されるので現状どうかはわかりませんが、wikipediaを見たところでは、Agathis dammaraという学名の樹木もありますね。さて、Plant Resinsによると、この樹の樹脂を現地ではダンマルと呼ぶが、市場ではコーパルと呼ばれるものであると書かれてあります。そのように樹脂名及び採取源の植物の名称の関係はパズルのように複雑に入れ乱れていますが、特に医療用途では個々の植物へのアレルギーなどありますので、深刻な問題のようです。画材店向けではあり得ませんが、アロマ用品のショップでは「ダンマーコーパル」という商品があったりして不思議に思ったことがありますが、ダンマーを樹脂全般の意味で使ったとしたら、そんなにコーパル樹脂ぐらいの意味で、とくにおかしなことはないのかしれません。いずれにしても、画材店で販売されているものを利用する分には、専門家が取り扱っているものなので、特に名称の問題や採取源など気にすることはないですけれども。 語源の事で触れられたダンマーを利用した燈火ですが、Plant Resinでは、マレー人の古来からの使用法として照明に関して触れています。粉砕したダンマル樹脂をバークチップやウッドオイルと混ぜて、パームの葉で包み、0.6mからそこらの長さの円筒状の細いロウソクにすると書かれてあります。 こんな情報なんの役に立つのかわかりませんが、しかし、マスチックは聖書などの書物に登場し、ダンマルは釈迦入滅の際に出てくる樹木から採れるということで、世界史、特に古代史が好きな私としてたいへん興味深いところです。 |
|
2016,08,11, Thursday
お盆休み的なものに突入するし、普段は読む気にならないような分厚い洋書の1冊でも読んでおかなければいけないような気がして、今回は以下に挑戦してみることにしました。
Jean H. Langenheim(著)”Plant Resins: Chemistry, Evolution, Ecology, and Ethnobotany”Timber Pr (2003/4/30) 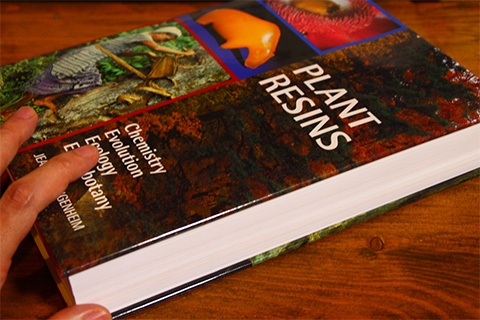 ハードカバー: 586ページでボリューム感がありますが、でも、絵画に使われている樹脂はある程度限られているので、必要な部分をピックアップして読んでいくわけですが、鳥越一穂氏と樹脂に関する動画を撮ろうと計画しているところなので、むしろパパパっと素早く目を通さねばならないのかもしれません。樹脂に使用に関しては、実際にいろいろ試しているので、それなりの経験に基づいて語れますが、それらの樹脂はいずれも遠い国から輸入されてきたものであって、実際どういう木から採れるものかというのをあまり知らないので、そういう点を整理しておきたいという気持ちが以前からあったのですが。 ひとまず、マスチック樹脂の項から読み始めました。我らがマスチックは、Pistacia lentiscusから採取される樹脂だそうですが、この木はウルシ科のカイノキ属。針葉樹の顕花植物で、常緑で雄雌異株(オスとメスで別れる)とあります。地中海全般に分布するようだが、中世に主にマスチック樹脂が採取されたのはキオス島のものだという。和名ではカイノキが最も近そうで、苗も売られているのですが、しかし落葉高木だったり、いろんな種類があって、頭を整理するのは大変そうです。 youtubeにはPistacia lentiscusの盆栽の映像が投稿されています。 木の形はウルシとは似てないけれども、葉の並び方はウルシタイプですね。Pistacia lentiscusの苗、日本で手に入るなら是非とも欲しいところです。 Pistacia lentiscusの動画らしきもの↓ Pistaciaという名前の通り、ピスタチオの実がなる樹木の仲間であるようである。ただし、お酒のつまみとしても食されるピスタチオの実が成るのはPiatacia veraという種類であり、マスチックの木の実の方は、ちょっと違うようである。 Piatacia veraの動画らしきもの↓ 話が逸れるけれども、興味深いのはテレビンノキとして知られるPistacia terebinthus。テレビンと言えば、カラマツ属、モミ属などの大きなマツ科の針葉樹から採取されるもというイメージが強いが、初期にはこのテレビンノキから採られていたものらしい。ふと気になって、チェンニーニがウルトラマリン抽出で試用していた松脂はどんなものかと思ってイタリア語の刊行版をあたってみたが、pinoの樹脂と書かれてあったので、これに関しては松から採られたのだろう。ちなみに、テレビンノキは旧約聖書に登場する。 Pistacia terebinthusの動画らしきもの↓ マスチック生産は、キオス島と言っても島の東南の角、Pistacia lentiscus Var. chiaが生い茂る箇所に限定されるようで、他の場所で採取されたものは、しっかり育った木から得たものでも質は劣るということである。ということは良質のものは供給量が限られるので、価格が高いのも仕方がないかもしれないし、絵画用のマスチック樹脂でも、質の良いもの、悪いものなど差があるのは、この辺にも起因するかもしれない。雄雌異株と書いたが、マスチック採取に使われるのは雄株の方で、雌株の樹脂は劣っている。さて、PLANT RESINSではこの後は実際の採取方法、用途や歴史などについて延々と述べられており、絵画用としては、リンシードオイル、揮発性のテレビン油などと混ぜてゼリー状のいわゆるメギルプを作るというところまで書かれてあり、興味は尽きないところですが、化学的な部分はなんだかんだで読むのが難しい。 |
↑上に戻る↑ :


