|
2010,01,20, Wednesday
■前回■アラビアゴムで木工してみる。
http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=702 前回、アラビアゴムを接着剤にしつつ、軽く木工などを試みたが、今回はその上にアラビアゴムを媒材とした塗料を塗ってみることに。アラビアゴムは水彩絵具の媒材であるからして、実質的には水彩絵具(あるいはガッシュ)を塗るのと同じであろうけれども、油絵野郎なので水彩絵具はほとんど手元に無く、しかし顔料はいっぱいあるので、これとアラビアゴム水溶液を混ぜて塗るわけである。 まず、アラビアゴム水溶液とアンバー顔料を混ぜ合わせる。  刷毛で塗料を置き、ウエスで擦り込むように塗布。  いまいち塗料の伸びが良くないが、擦り擦りしているうちに、なんとかそれなりになってきた。  乾燥後、改めて眺めて見るものの、あまり綺麗ではないような。。。  塗りむらが酷く、磨く前の焼き板のような感じである。まぁ、慣れてないってのもあるが。。白い地塗の上ならば水彩絵具のように映えるのかもしれないが、板に直接塗布すると、今ひとつ引き立たないような感じがしないでもない。以前、度々試みたミルクペイントの方が塗りやすかったし、木材が映えるような。 話が逸れるが、先日、Understanding Wood Finishing: How to Select and Apply the Right Finishなる本を買ったばかりというのに、さらにTraditional Finishing Techniques (New Best of Fine Woodworking)という本も買ってしまったんだけど、それをパラパラめくっていたら、ミルクペイントが載っていた。 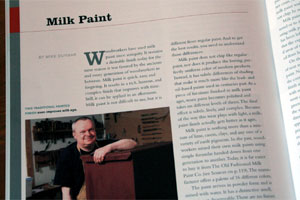 さすがに牛乳と顔料を混ぜるようなものではなくて、ちゃんとした既製品を使用しているが。 話は戻って、シェラックニスを塗る。   何層も塗っていたらテカリがひどくなったので、サンドペーパーで擦る。 壁に取り付けて完成。  机の上の小物を置く為の棚が欲しかったという、ただそれだけの話でした。 |
|
2009,12,20, Sunday
蜜蝋というと、個人的には油絵具の展色材やら加筆用メディウム等にかなりの頻度で使用しているのだけれども、そう言えば、それ以外の用途にはあまり使ったことがなかった。一応それなりに知っているように感じている事柄でも、普段やってることと少しでも外れると、まるで手も足も出ない未知の世界ですわなぁとか思いつつ、蜜蝋をちょっと弄ってみようかと思い立つ。
で、ここになんとなく投げやりな感じで作られた素木の棚がある。  自分が作った棚じゃないんだけど、これを使っていろいろいニスやらワックスやら試してみよう。 第一段階はミルクペイントで色付け。  顔料はキプロス島ローアンバーと同バーントアンバー。それと牛乳。 なお、牛乳はなんとなく電子レンジで3分熱したんだが、何の意味があるかはわからない。前もこうやって一応成功しているので。 牛乳に顔料を入れて混ぜたところ。   刷毛でドバッと塗ったが、サンディングとか木の表明調整を全くやっていなかったので、塗料のノリが悪い。しかも色が濃過ぎ。 布で擦りつけて塗ることにした。  塗装後。  割といい雰囲気である。牛乳で一応顔料がくっついているというのは何度見ても感心する。 塗装が乾いたところで、第二段階としてシェラックニスを。  カイガラムシ分泌物を、アルコールで溶いたものである(前日仕込んでおいた)。  ちなみに、100均の刷毛を使用。近所の100均の刷毛は私が買い占めてしまった。昔は毛が抜けたりして品質が悪かったが、最近は普通に使えるものが多い。 計二回塗ったが、なんかギラギラつやつやである。  いよいよ第三段階にて蜜蝋登場。  一応、こんな感じで手元に3種類の蜜蝋がある。左は、先日、キガタドットコムさんで購入したもので、最も色が濃い。蜂蜜っぽいような感じの香りがムワっとしてくる。芯でも挿したらそのままロウソクになりそうな。。とか言いつつ、今回は真ん中の蜜蝋(クレマー?)を使用。 蜜蝋を溶かす方法はいろいろありそうだが、というか、実際いろいろ試したんだが、それを書いてると長くなるので今は端折らせてもらうと、結局、電気保温プレートが最も手軽な気がした。  蜜蝋とテレピンを入れた器を保温プレート上に置いて、数分眺めていただけだが、わりと易々と溶解してくれた。この手の製品は保温という目的以上の温度は出ないので、わりと安全だと思うのだが保証はできないので、自己責任でどうぞ。 冷えると、以下な感じに。  冷えても固まるということはなくて、柔らかい練り物みたいなようなものになった。これを毛の落ちない布などで、表面に擦りつけるなどするといいらしい。 といいつつ、私は思わず、温度の高いうちに刷毛で塗ってみた。  これは濃度とかいろいろ考えないと、ちょっとあまりにも塗りすぎになってしまうなと感じで、すぐに布での塗布に切り替えた。  塗りすぎると、本当にいろいろ困るので、ご注意を。 うまくいったのかどうかわからないけれど、とりあえず終了。  参考: http://kigata.com/beeswax.htm |
↑上に戻る↑ :


